【未来からほめられるアクション4】 家族と自身の健康について考えよう

2025_SCOPEカレンダー連携コラム
2025年スコープカレンダーでは、毎月、サステナブルな記念日をピックアップし『未来からほめられるアクション』と共にご紹介しています。4月の記念日は4月7日の「世界健康デー(World Health Day)」。これは1948年に世界保健機関(WHO)が設立された日を記念して、2年後の1950年に定められた国際デーです。
※2025年2月、日本WHO協会より「「World Health Day」の訳を「「世界保健デー」から「世界健康デー」に変更する旨の発表がありました。SCOPEカレンダーには変更前の訳語「世界保健デー」と記載されております。
家族や自分の健康、そして私たちが見落としがちな生活習慣やセルフケアを改めて考える機会として、さまざまな関連イベントや啓発キャンペーンが世界各地で行われています。今回は「世界健康デー」の意義やテーマ、そして私たちが日々の暮らしの中で取り組めるアクションをご紹介します。
■「世界保健デー」は2025年から新訳「世界健康デー」に
「World Health Day」を、日本WHOではこれまで「世界保健デー」と翻訳してきましたが、医療関係者のための記念日という印象が強かったため、2025年からは「世界健康デー」と訳を改めました。子どもから高齢者まで一般市民のための記念日であることを伝えることが目的です。
この「世界健康デー」は、WHO(世界保健機関)の理念を世界中で共有し、健康増進への意識を高めることを目的とした国際デーです。WHOは「すべての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を理念として掲げており、各国政府や地域コミュニティ、個人に対して、その年ごとに定めたテーマに基づいた活動を呼びかけています。
歴史的にみても、感染症対策や栄養改善、医療体制の強化など、健康にまつわる課題は時代とともに姿を変えてきました。近年は新型感染症の影響もあり、手洗いや手指消毒など基本的な衛生管理の重要性が再認識され、イベントでも取り上げられる機会が増えています。あらためて、世界健康デーは、医療関係者のみならず、一般市民にとって身近な「健康」をあらためて見つめ直し、家族や自分の生活習慣を見直す機会であると言えるでしょう。
■2024年までの「世界保健デー」のテーマの変遷
テーマやスローガンは、毎年3月にWHOから発表されます。テーマの変遷を振り返ると、感染症対策、メンタルヘルス、生活習慣病など、時代のニーズに合わせて設定されてきました。
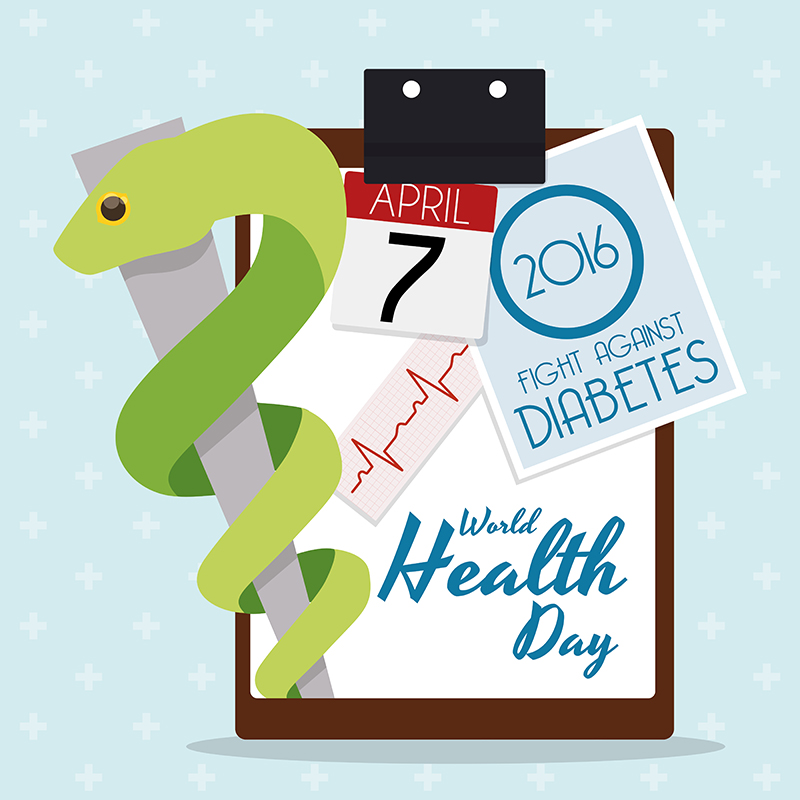
特定の病気にフォーカスした年もあり、例えば2016年は「糖尿病(Diabetes:ダイアベティス)に負けるな」というスローガンで、食生活や運動習慣の見直しを提案するキャンペーンが行われました。

また2017年は「うつ病(Depression:デプレッション)」をテーマとし、うつ病対策について啓発し、多忙な現代人に向けてうつ病の予防やケアの方法などが紹介されました。
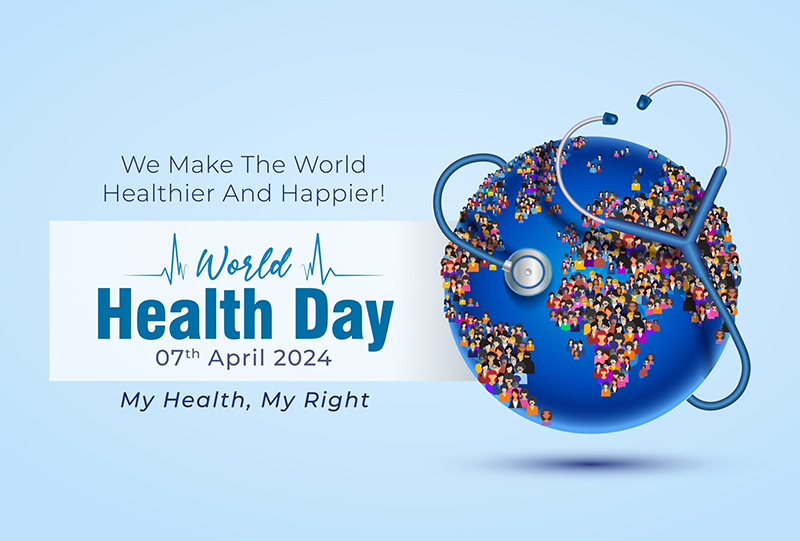
2024年のテーマは「私の健康、私の権利」でした。私たちの健康は単に身体だけの問題ではなく、きれいな空気や安全な水、良質な栄養、質の高い住宅、人間らしい労働、医療サービスへのアクセスなど、包括的に守られるべきであり、社会全体の責務が問われるというものです。このように単に医療の話に留まらず、私たちの暮らし全体に深く関わっているのが特徴です。
■今年のテーマと関連イベント

2025年のテーマは「Healthy beginnings, hopeful futures(健やかなはじまり、希望のある未来へ)」。母子の健康にスポットを当て、妊娠や出産にまつわる予防可能な死亡をなくし、女性の健康と福祉を最優先に考えるよう、各国政府や医療界に呼びかけています。
妊娠や出産をめぐる現状は深刻です。世界では毎年およそ30万人もの女性が妊産婦として命を落とし、生後1カ月以内に200万以上の赤ちゃんが死亡している上、多数の死産も起きています。SDGsターゲット3.1「妊産婦死亡率の削減」では、2030年までに世界の妊産婦の死亡率を出生10万人当たり70人未満に削減するとしていますが、残念ながら今のペースでは削減目標を達成できない国が5分の4ほどになる見込みです。
2025年の世界健康デーは、この問題をクローズアップし、解決へ向けた取り組みを世界規模で加速させる大切な機会となるでしょう。WHOをはじめとする関連団体は、妊娠・出産期、そして産後までのトータルなケアを支援するため、さまざまな情報を発信する予定です。
国内でも、自治体や医療系NPO、学会などが開催するフォーラムやセミナーが予定されており、多くの市民や専門家が意見を交わす場となる見込みです。
日本WHO協会は世界健康デーを「健康の日」として広める取り組みを進めており、4月7日に「WHO世界健康デー2025」を開催します。こうした場で共有される知恵や経験が、お母さんと赤ちゃんの健康を守る新たな一歩につながることが期待されています。
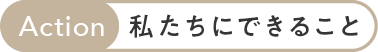

(引用 WHO公式サイト) https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2025
まず、4月7日から始まるキャンペーンに参加することができます。WHOのサイトでは、ハッシュタグをつけて情報発信し「意識を広める」、世界規模のイベントに「参加する」ことで妊婦・新生児死亡率を下げるために必要なことを学ぶ、WHO財団に「寄付する」、インスタグラムで「個人的な経験を共有する」という4つのアクションを促しています。

(引用サイト 日本WHO協会)https://japan-who.or.jp/about-us/notice/2503-7/
また、日本WHOが主催するイベント「WHO世界健康デー2025」に参加するのもいいですね。4月7日(日)14:00~16:30、大阪市の会場とオンラインのハイブリッド開催となっています。(参加費無料)
そして、この機に、我が国の「母子の健康」について考えてみるのはいかがでしょうか。すべての母子が安心して暮らせる環境をつくるには、行政、企業のみならず、家族や地域社会、医療機関が一緒になって支えることが大切です。女性の声にしっかり耳を傾け、働き方や生活環境、医療サービスのあり方まで見直す総合的な取り組みが求められています。そんな中で、一市民である私たち一人ひとりは、妊婦さんや子育て中の女性に、「何か困っていない?」と声をかけることができます。
こうした小さな行動の積み重ねで、お母さんと赤ちゃんを取り巻く環境は明るく変わっていきます。すべてのお母さんと赤ちゃんが安全に暮らせる社会を築くことは、未来からほめられるアクションにつながるはずです。

