【未来からほめられるアクション11】 子どもたちの幸せを考える

2025_SCOPEカレンダー連携コラム
私たちスコープグループは、社会課題の解決を目標に「発想力と実現力で、未来からほめられる仕事を。」というパーパスを掲げ、ワクワクが持続する社会の実現をめざして企業活動を推進しています。グループのPRツールとして頒布した「2025年スコープカレンダー」では、毎月、サステナブルな記念日をご紹介し『未来からほめられるアクション』をご提案しています。
カレンダーと連携した今回のWebコラムでは、国連が定めた11月20日の「世界こどもの日(World Children’s Day)」についてご紹介します。
■世界こどもの日の起源と意義
世界こどもの日は1954年に国連で制定され、1989年の11月20日に「子どもの権利条約」が採択されました。条約は子どもを「権利を持つ主体」として位置づけ、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の四つの柱を通じて、子どもが安全に育ち、教育を受け、差別や虐待から守られることを求めます。

出典:子どもの権利条約採択30年記念ポスター
(https://www.unicef.or.jp/crc/tools/)
この日は世界各地で教育プログラムや公開イベントが行われます。
日本ユニセフ協会は毎年、子どもの権利をテーマにした動画やSNSキャンペーンを展開しています。2024年は、法務省と連携し、スペシャル動画「ジーン&ケーンといっしょに考えよう!『人権週間』と『こどものけんり』」を公開しました。また、多くの学校で子どもの権利への理解を深める授業やワークショップが行われます。児童館、公民館などで、子どもたちが自分の意見を表現したり、意見交換したりする場が設けられています。
■世界の象徴的な若者と日本のムーブメント
世界では、一人の若者の行動が瞬時に注目を集めて議論を動かすことがあります。グレタさんらの世界の目をひく活動と日本で広がる現場の動きの関連性を見てみましょう。

グレタ・トゥーンベリさん
(第6条【生きる権利・育つ権利】で考察)
(写真:2019年 ベルリンにて)
2003年生まれのグレタさんは、2018年にスウェーデンの国会前で始めた学校ストライキを契機に「Fridays for Future」を世界へ広げ、国連やCOPの場で、気候変動が子どもたちの生存に深刻な影響を与えることを訴え、未来を守る権利を国際議論の場に押し上げました。
グレタさんの始めた活動は、日本では学生主体の「Fridays For Future Japan」や、海洋ごみ削減を掲げる「SEA CHANGE(シーチェンジ)」に受け継がれました。各団体は、地域の学習会や海岸清掃を継続し、自治体との協働を進めています。

アマンダ・ゴーマンさん
(第15条 【結社・集会の自由】で考察)
(写真:2024年シカゴにて)
1998年生まれのアマンダさんは2017年にアメリカ議会図書館が創設したプログラム「全米青年桂冠詩人(National Youth Poet Laureate)」に選ばれ、有名になりました。2021年のバイデン大統領就任式で詩人として「わたしたちが登る丘(The Hill We Climb)」を朗読する詩人に抜擢されました。アマンダさんは、文化的活動を通じて社会に参加し、声を上げることの象徴となっています。
日本では「東京都子ども会議」や市区町村レベルの子ども議会、若者の政策提言を支援する「日本版ユース・パーラメント」が若者の声を政策に届ける場を提供しています。また、学校の公開討論や地域の表現フェス、SNSを使った匿名相談窓口など、多様な場で、従来の制度では拾いにくかった声がキャッチされています。

マララ・ユスフザイさん
(第28条【教育を受ける権利】で考察)
(写真:2023年 ロサンゼルスにて)
1997年生まれのマララさんは、中学生の時、女子教育の権利を訴えタリバンに銃撃されるも生還。世界中に女子教育の普遍性を訴え、2014年に最年少でノーベル平和賞を受賞しました。マララさんの活動は、子どもたちの教育へのアクセス確保に大きな影響を与えています。
日本では、放課後子ども教室(文部科学省・内閣府の支援事業)や自治体とNPOの連携による学習支援、大学生ボランティアによる家庭学習支援、奨学金制度や生活相談窓口の充実が進んできました。コロナ禍で浮き彫りになったデジタルデバイド(情報格差)への対応が、全国的にはGIGAスクール構想を加速させました。

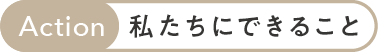
■ YouTubeで子どもの権利について学び、周囲の大人と共有する

ジーン&ケーン 学んでみよう!子どもの権利 ~みんなが大切にされる毎日を~ / 日本ユニセフ協会
https://www.youtube.com/watch?v=t_hq_cB5GY0
子どもの権利について、基本から学んでみませんか。家族、職場、学校などでまずは動画を一度再生して、感想を共有してみましょう。日本ユニセフ協会のYouTubeチャンネルは、子どもの権利やウェルビーイングについて考える有益な教材となっています。
■ 集いの場では大人は聞き手に徹する
学校の子ども議会や学級討論、地域の子どもミーティングを開くときは、大人が場づくりと見守りに徹しましょう。会場準備や記録、発言の可視化(付箋やホワイトボード)を手伝うだけで子どもは安心して話せます。まずは学校や地域の担当者に「会場の手伝いならできます」と声をかけてみてください。
■ 通学路を把握して交通安全を促す
無理なくできる身近な支援は通学路の安全確認です。通学時間に通学路を歩き、見通しの悪い交差点や路肩の狭い箇所、夜間に暗い街路灯など危険箇所を写真や地図で記録し、学校・PTA・自治会・交番に共有しましょう。一度、通学路を歩いて危険箇所をメモすることから始めましょう。
■ 地域のお祭りに参加する
お祭りは子どもと家族が集まる良い機会です。子どもブースで読み聞かせや工作を担当したり、迷子対応の連絡ステーションを設けたりするだけでも子どもの安心につながります。孤立しがちな家庭に声をかけるチャンスでもあり、寄付やフードドライブ、子ども支援団体の周知に結びつけられます。写真撮影や個人情報の扱いは保護者同意を徹底し、子どもが安心して楽しめる配慮を忘れずに。まずは地域の主催者に「子どもブースを手伝えます」と申し出てみましょう。
■ フードドライブで食の安心を届ける

未開封で賞味期限に余裕のある常温保存可能な食品(缶詰、乾麺、レトルトなど)を集め、子ども食堂やフードバンクへ寄付するフードドライブは取り組みやすい支援です。開催前に受け入れ先のガイドラインを確認し、集める品目・賞味期限を明示しましょう。生鮮や手作りは原則避け、アレルギー表示のあるものはラベルを添えて提供するのが安心です。まずは受け入れ先へ問い合わせて、日程と受け取り条件を確認してみてください。
子どもたちの未来を守るために
世界こどもの日は、1989年の「子どもの権利条約」採択日を起点に、子どもを「権利を持つ主体」として守り、育て、参加の機会を保障することを改めて考える日です。気候変動や表現の自由、教育の普及といったテーマで世界に影響を与えたグレタさんら若者の行動は、“子どもたちの声が社会を動かす力になる”ことを示しています。日本でも子ども議会や放課後支援、学習ボランティアといった現場の取り組みが進み、地域や学校での実践が重要です。
また“子どもの支援の視点”は、プライバシーと安全を最優先に、短期で終わらせず継続的に関わることが重要です。家庭や学校、地域での小さな一歩が、子どもたちの自己肯定感と社会参加意識を育み、未来からほめられる社会につながります。

