【未来からほめられるアクション2】 思いやりの心で、相互理解を深めよう
2025_SCOPEカレンダー連携コラム
2025年スコープカレンダーでは毎月、サステナブルな記念日をピックアップし「未来からほめられるアクション」と共にご紹介しています。2月の記念日は2月4日の「国際友愛デー」。すべての人権を尊重することを目的としたこの日に、私たちができるアクションについて考えてみましょう。

■『国際友愛デー』とは
2月4日は「国際友愛デー(International Day of Human Fraternity)」です。国籍や性別、宗教、文化の違いを超えて、すべての人の人権を尊重し、友情を育むことを目的にした記念日として、2020年に国連によって制定されました。
この記念日の意義を象徴的に表したのが、2024年にアラブ首長国連邦のアブダビで開催された記念式典でのフランシスコ・ローマ法王のメッセージです。法王は「友愛の道は、長く険しい共に歩む道のりですが、それは人類にとっての救いの錨(いかり)となるものです。今、私たちが直面している様々な困難や暗い時代に立ち向かうために、この友愛の精神が必要なのです」と語りかけました。
また法王は、現代社会が抱える課題にも言及し、「人々の間の連帯感が失われることで、環境破壊や社会の分断が進み、多くの人々が苦しみを抱えることになっている」と指摘しています。私たち一人ひとりが互いを思いやり、支え合う関係を築いていくことの大切さを訴えかけたのです。
互いを思いやり、支え合える社会をつくるためにはどうすればよいのでしょうか。人権の尊重というと難しく感じますが、私たちにできることを一緒に見つけていきましょう。
■「人権を尊重する」とは
人権を尊重するということは、誰もが生まれながらに持つ基本的な権利を認め、守ることです。これは、人種・国籍・性別・出身・職業・年齢などに関係なく、すべての人を平等に扱うことを意味します。

しかし、実際には世界ではいまも深刻な人権侵害が行われています。
たとえば少数民族が政治的、経済的に排除され、教育や就労の機会を奪われるケースや、一部の国々では、特定の民族グループが差別や迫害を受け、基本的人権が侵害されている現実もあります。言語や文化、伝統が異なるというだけで、社会から疎外され、尊厳を傷つけられている人々がいるのです。
また、性別による差別も私たちの身近なところに存在しています。女性の多くは職場での昇進機会が限られ、同じ仕事でも賃金に差をつけられるなど、不平等な状況に直面しています。「女性だから」という理由でキャリアを諦め、家事育児に専念せざるを得ない状況に置かれる人も少なくありません。一方で男性も「男性だから」という理由で、家族を守るために働き続けなければならないというプレッシャーを感じています。「稼がなければ」「家族を養わなければ」という責任感から仕事優先の生活になり、家族との大切な時間も育児休暇も取れないという現実があります。
このような性別による格差(ジェンダー不平等)は、人権侵害につながるとして、世界中で取り上げられています。

子どもたちへの人権侵害も深刻な問題です。世界では今も児童労働や児童婚、教育機会の剥奪、性的搾取、紛争地域での徴兵など、子どもたちの健やかな成長と安全が脅かされています。
日本でも子どもたちの人権は社会問題になっています。2022年時点では約9人に1人の子どもが貧困状態にあり、経済的な理由で教育や習い事、部活動を諦めざるを得ない状況に置かれています。また、虐待や育児放棄(ネグレクト)の報告件数は年々増加傾向にあり、SNSを通じた性被害やいじめの問題も後を絶ちません。さらに、ヤングケアラーと呼ばれる、家族の介護や世話を担う子どもたちの存在も明らかになってきています。
人権について、私たちはつい「難しいもの」「遠いもの」と考えがちです。でも実は、会社での何気ない会話、学校でのふとした出来事、家庭での日々のやりとり、そのすべてに人権問題は関わっています。
一人ひとりの生き方や考え方はみんな違う。その違いを認め合い、お互いを思いやる気持ちを持つこと。それが人権を守る第一歩なのかもしれません。誰もが自分らしく生きられる社会は、私たち一人ひとりのそんな小さな思いやりから始まるのではないでしょうか。
■偏見や差別の原因を知ろう
私たちの周りにある偏見や差別の多くは、相手のことをよく知らないことから始まります。見た目が違う、文化が違う、考え方が違う――そのような「違い」への不安や誤解が、時として差別やいじめにつながってしまうことがあります。
学校でのいじめ、職場でのハラスメント、地域社会での差別的な態度。これらは決して特別な場所の出来事ではなく、私たちの日常生活のあらゆる場面に潜んでいます。偏見や差別の背景は多くの場合、相手との「違い」を受け入れられない気持ちや、理解できないことからの不安からくるのかもしれません。他者への理解不足や誤った先入観が、心の中に偏見を生み、やがて差別やいじめという形で現れてしまいます。しかし相手を知り、理解する努力を重ねることで、こうした偏見は乗り越えられる可能性があります。
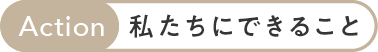

国連のSDGs目標10「人や国の不平等をなくそう」は、世界全体が取り組むべき問題として、すべての人が生まれや性別、宗教などに関係なく平等に生活できる世界を目指すと示されています。
差別をなくすための第一歩は、互いを理解すること。「国際友愛デー」に、私たちにできることを考えてみませんか。身近な人々との会話の中で、違いに対する偏見や誤解を和らげるきっかけを作ることもその一つです。また、学校や職場で話し合う機会を作ってみることもすばらしい取り組みです。
国際的な課題にも目を向けてみましょう。寄付やクラウドファンディングを通じて、人権問題に取り組む団体を支援したり、SNSでの情報発信を行ったりすることで、より多くの人々と問題意識を共有することができるでしょう。
小さな意識の変化、小さな行動がやがて大きな変化を生み出します。この国際友愛デーをきっかけに、私たち一人ひとりが互いの尊厳を認め合い、未来からほめられるアクションを起こしていきましょう。私たちの小さな一歩が、より良い未来への架け橋となるはずです。

